Volume 22, No.4 Pages 336 - 339
2. 研究会等報告/WORKSHOP AND COMMITTEE REPORT
第14回SPring-8産業利用報告会
The 14th Joint Conference on Industrial Applications of SPring-8
1. はじめに
産業用専用ビームライン建設利用共同体(サンビーム共同体)、兵庫県、(株)豊田中央研究所、(公財)高輝度光科学研究センター(JASRI)、SPring-8利用推進協議会(推進協)の5団体の主催、及びフロンティアソフトマター開発専用ビームライン産学連合体(FSBL)、SPRUC企業利用研究会、光ビームプラットフォーム、(一財)総合科学研究機構中性子科学センター(CROSS東海)、(一財)高度情報科学技術研究機構(RIST)、茨城県、あいちシンクロトロン光センターの協賛で第14回SPring-8産業利用報告会が8月31日、9月1日に川崎市産業振興会館において開催された。
本報告会は主催団体の4団体(サンビーム、兵庫県、(株)豊田中央研究所、JASRI)がそれぞれ運用する専用及び共用ビームラインにおける成果の報告会のジョイントとして構成され、その目的は(1)産業界における放射光の有用性を広報するとともに、(2)SPring-8の産業利用者の相互交流と情報交換を促進することにある。また、SPring-8立地自治体の兵庫県がSPring-8の社会全体における認識と知名度を高める目的で2003年度より設置した「ひょうごSPring-8賞」の第15回受賞記念講演が今年も併催された。
2004年の開催から14回を数える今回の総参加者は258名で、口頭発表やポスター発表、技術交流会において活発な議論と産業分野を跨いだ交流が行われ、今回も前述の開催目的に沿った、SPring-8の産業利用の「今」を伝える最良の情報発信の機会となった。
2. 口頭発表(1日目)
報告会1日目の口頭発表は、8月31日の午後1時より会場1階の大ホールにおいて行われた。最初のセッション1の開催挨拶は、主催団体を代表してJASRIの土肥理事長から挨拶があり、SPring-8の産業利用の状況として、(1)産業利用としての成果に対する評価指針の確立が求められていること、(2)評価軸として投稿論文件数だけでなく利用料収入についても情報公開を行うことにしたこと、(3)利用料収入についてさらなる拡大を政府から期待されていること、などが説明された。このように成果に対する要求が厳しくなる中で、産業界においても可能な限りトピックスを発表して利用成果をアピールしてほしいとの希望が述べられた。
次のセッション2では、「兵庫県成果報告会」が行われた。まず篭島放射光ナノテクセンター長から、SPring-8の兵庫県ビームライン(BL08B2、BL24XU)とニュースバルの現状の概要について報告があり、その後、これら施設の利用成果について5件の発表があった。
最初の発表は、グローバルウェーハズ・ジャパン(株)の堀川氏より、「放射光X線散漫散乱法によるSi結晶中の酸素析出物解析」というタイトルで、半導体デバイスの基板であるCZ-Siウェハーの製造において課題となる酸化物の析出物分布制御技術向上のための知見を得るために、サンプルの斜め研磨技術と組み合わせたX線散漫散乱測定による析出物の密度、及びサイズ深さ分布評価技術の検討を行った結果について報告があった。(株)アシックスの立石氏からは、「ワンショット法ポリエチレン化学発泡成形プロセスのX線イメージング」というタイトルで、靴底のスポンジ材の製造法で樹脂の架橋と発泡を同時で行う表題の発泡プロセスにおける、スポンジの気泡構造の時間変化をX線透過イメージングで追跡観察を行った成果を発表された。日本電気(株)の弓削氏からは、「放射光を用いた鉄系Li過剰層状正極の充放電挙動解析」というタイトルで、高容量、高信頼性、低コストを実現する2次電池正極材料として期待されているFe、Ni固溶Li2MnO3の電池の充放電過程における構造変化について、セルを解体して得られた電極サンプルを用い、放射光を用いたX線吸収微細構造(XAFS)及び硬X線光電子分光(HAXPES)測定と、粉末X線及び中性子回折、57Feメスバウアー測定を併用して評価を行った成果について報告された。兵庫県立大の高山先生からは、「BL24XUにおけるコヒーレントX線回折を利用したX線ナノイメージング法の開発」というタイトルで、BL24XUで開発中のコヒーレントX線回折イメージング装置について、金コロイド粒子やマイクロポーラスシリカに対する応用事例を基に紹介された。兵庫県立大の渡邊先生からは、「NewSUBARUに於ける極端紫外線リソグラフィ技術開発」というタイトルで、ニュースバルのビームラインBL3、BL9、BL10で進められている半導体デバイスの線幅10 nmを目指した極端紫外線リソグラフィ技術の開発研究について紹介された。
セッション3の「第17回サンビーム研究発表会」では、サンビーム共同体幹事の三菱電機(株)の河瀬氏から報告された共同体の活動趣旨説明の後、同共同体が運用するSPring-8の産業用専用ビームライン、サンビーム(BL16B2、BL16XU)を利用した共同体参加企業の成果について5件の発表があった。
最初に三菱電機(株)の田中氏から、「硬X線光電子分光法による酸化膜/Si基板界面の欠陥密度評価」というタイトルで、MOSFETのゲート絶縁膜製造プロセスにおけるArプラズマ処理の絶縁膜/基板界面の界面準位・欠陥密度に対する影響を電圧印加HAXPES測定によって評価した結果について報告された。(株)富士通研究所の野村氏からは、「IoT市場向け強誘電体メモリ(FRAM)におけるPLZT薄膜の結晶化メカニズム」というタイトルで、FRAM用のPbLa(Zr,Ti)O3(PLZT)強誘電体膜の結晶構造の結晶化アニールプロセスの雰囲気組成依存性をX線回折(XRD)とXAFSを併用して検討した結果が報告され、このアニール雰囲気制御がFRAMの分極特性に影響するメカニズムについて議論された。(株)日立製作所の米山氏からは、「走査型X線顕微鏡を用いたマイクロトポグラフィーの検討」というタイトルで、BL16XUで開発された走査型X線顕微鏡のマイクロトポグラフィーによるSiCウェハーの転位分布評価への応用事例の紹介がなされた。住友電気工業(株)の久保氏からは、「硬X線光電子分光による金属/高分子界面の密着機構の調査」というタイトルで、機械摺動部材の表面コーティング用の架橋フッ素樹脂膜が電子線照射により耐摩耗性及び金属基材との密着性が向上するメカニズムについて、放射光を用いたHAXPES測定と、STEM、EDXを併用して検討した結果が報告された。川崎重工業(株)の根上氏からは、「耐熱合金表面の酸化物生成挙動の評価」というタイトルで、ガスタービンエンジンの高効率化(燃焼ガス高温化)開発において課題となる耐熱合金表面コーティングの耐酸化性向上について、その耐酸化機能を担うボンドコート層のNiCoCrAlY合金の高温腐食挙動の雰囲気依存性を、高温下in-situ XRD測定により評価した結果から、Al酸化物生成挙動に対する酸素分圧の影響について議論された。

図1 口頭発表の様子
3. 技術交流会
この後行われた技術交流会では、総参加者の約半数近くの111名が参加し、活気あふれる雰囲気の中で行われた。例年同様、産業分野と産学官の所属を跨いだ、幅広いSPring-8利用者間の熱い交流が行われ、正にSPring-8産業利用の「多様性」を象徴する会となった。
4. 口頭発表(2日目)
2日目は、午前9時30分より口頭発表のセッション4「JASRI共用ビームライン実施課題報告会」から始まった。最初にJASRI産業利用推進室の廣沢室長による「2016年度共用ビームライン産業利用分野の現状」の報告が行われた後、金属、自動車、電子デバイス、2次電池、食品と多様な分野での、XRD、イメージング、HAXPES、XAFS、X線小角散乱(SAXS)など多岐にわたる手法を用いた5件の共用ビームラインの利用成果が報告された。
まず新日鐵住金ステンレス(株)の秦野氏から、「放射光X線を活用したSUS304鋼の水素脆化に係る微細構造解析」というタイトルで、水素社会インフラ整備において重要な課題であるステンレス(SUS304鋼材)の水素脆化について、水素添加して引張変形を印加したSUS304鋼試験片のXRD測定をBL02B2で行い、水素添加によって母相(γ相)から実験室系のXRD装置では検出できないほど極微量のε相への加工誘起変態が促進されていることを示す結果を得たことについて報告され、この加工誘起変態相と水素脆化発生メカニズムの相関について議論された。ダイハツ工業(株)の中山氏からは、「自動車メタリック塗装のイメージング観察」というタイトルで、自動車の車体への樹脂部品採用拡大に伴って重要となってきている鋼板部品と樹脂部品の塗装色合わせについて、メタリック塗装の色合いに影響を及ぼす塗膜中のアルミフレークの配向の塗装プロセス中の挙動をBL46XUにおいてX線透過イメージング測定により観察し、その影響因子を検討した結果を報告された。住友電気工業(株)の館野氏からは、「硬X線光電子分光を用いた高周波デバイスの状態解析」というタイトルで、次世代のTHz通信をターゲットとした高周波デバイスとして期待されているグラフェントランジスタについて、SiC基板上にエピタキシャル成長させたグラフェンのバンドポテンシャル深さ分布や、表面に製膜した絶縁膜界面の状態をBL46XUにおけるHAXPES測定によって評価した結果を報告され、その成膜プロセス依存性などについて議論された。東京理科大の駒場先生からは、「ナトリウムイオン蓄電池用Na-Ni-Mn系層状酸化物正極の充放電機構」というタイトルで、資源枯渇リスクのあるLi、Coを用いた現行の2次電池に対する代替電池として期待されるナトリウムイオン2次電池について、その劣化メカニズム解明を目的として、BL19B2における粉末XRD測定とBL14B2におけるXAFS測定により、Na-Ni-Mn系正極材料の結晶構造及び化学状態評価を行った結果について報告され、Ni添加により長寿命化するメカニズムについて議論された。森永乳業(株)の天羽氏からは、「プロセスチーズ溶融過程におけるカゼイン分子凝集体の微細構造変化」というタイトルで、プロセスチーズの加熱攪拌(クッキング)における増粘メカニズム解明のため、BL19B2におけるSAXS測定によりプロセスチーズ中の原材料である乳成分由来のカゼインミセルのクッキング中の凝集構造変化の評価を行い、そのクッキング条件依存性とチーズの粘度特性との相関について検討した結果について報告された。
昼食休憩の後、午後0時30分より開始されたセッション5の「第8回豊田ビームライン研究発表会」では、豊田ビームラインBL33XUにおいて豊田中央研究所が実施した研究成果2件が発表された。
1件目の上山氏の発表では、「放射光ラミノグラフィによる次世代パワーモジュール接合材の内部劣化挙動追跡計測」というタイトルで、ハイブリッド車や電気自動車の駆動電流の変換・制御を担うパワーモジュールの信頼性向上を目的とした疲労破壊メカニズム検討のため、冷熱疲労サイクル中のパワーモジュールの異種間接合部の亀裂進展挙動をラミノグラフィ法によるX線イメージング測定により動的観察を行った結果について報告された。2件目の田島氏の発表では、「コンビケミ薄膜試料を利用した高速・同時XRD-XRF分析」というタイトルで、マテリアルインフォマティクスによる新規材料探索において重要となる大規模な材料評価データベース構築を目的として開発された、大量の試料の高効率な測定を可能とする高速・同時XRD-蛍光X線(XRF)測定装置について紹介された。
セッション6の「ひょうごSPring-8賞受賞記念講演」は、ポスター発表をはさんで、午後3時20分より開催された。今年度はトヨタ自動車(株)の山重氏が、「リチウムイオン電池の反応分布その場リアルタイム観察手法の開発と応用」で受賞された。講演では、自動車産業におけるLiイオン電池開発の今後のトレンドと必要な開発事項について、さらに必要とされる分析対象の時間的、空間的スケールが広いことから分析手法や利用施設の特徴からその使い分けが重要であることを説明され、その研究事例として、作動中のLiイオン電池の電解液中のLiイオン移動に伴うその分布変化を、開発した模擬ラミネートセルを用いたX線イメージング測定によって動的に観察した成果を紹介された。
最後のセッション7では、高エネルギー加速器研究機構の野村昌治理事から報告会全体の講評をいただいた。まず、(1)報告された研究の対象分野の広がりからSPring-8の産業利用ユーザーが広がってきていること、また用いられている手法についても多様に広がってきているだけでなく、SPring-8の高輝度という特性を活かした先端的な技術も実用化されてきて、研究、発表の質が向上してきていること、が印象深く感じられたことが述べられた。ただ、(2)放射光の有用性が社会的に認識されて、その成果創出に期待が高まりつつある中で、個々の「放射光屋」による単なる施設利用から脱却できているかという懸念を述べられ、放射光コミュニティの中に蓄積されている知見を最大限に活かすには、施設スタッフとユーザー間、または産学を含めたユーザー同士、放射光施設間の連携を深めていくべきではないか、という提言をいただいた。さらに、(3)税金によって運用される大型施設を必要とする放射光利用は必ず社会的な責任を伴うものであり、特に非専有利用においては産業利用においても成果をPublicな財産にしていくことが必要である、という意見をいただいた。最後に、JASRI山川常務理事から閉会の挨拶が述べられ終了した。

図2 口頭発表の質疑応答の様子
5. ポスター発表
セッション5の後、ポスター発表が午後1時20分より50分ずつ2回のコアタイムを設けて会場4階の企画展示場で行われた。主催団体のサンビーム共同体から28件、兵庫県22件、豊田中央研究所8件、JASRI共用ビームライン30件、協賛のFSBLから2件の計90件のポスターに加えて、ひょうごSPring-8賞、あいちシンクロトロン光センター、兵庫県、茨城県、SPring-8利用推進協議会、SPRUC企業利用研究会、光ビームプラットフォーム、CROSS東海、RIST、JASRI産業利用推進室から合わせて11件の施設紹介や利用制度、利用者動向などのポスターが掲示された。今年は、(1)機器技術、(2)金属・構造材、(3)半導体・電子材料、(4)有機材料、(5)触媒・電気化学・エネルギー、(6)食品・日用品、(7)ビームライン、(8)その他、の分類で展示された。第11回よりこの分野別展示が実施されるようになってから、各分野で共通の興味を持つ参加者が集まりやすくなり、より充実した議論が交わされるようになったが、さらに自分の分野と違う分野のポスターの前で質疑をしている参加者も見られ、分野間の交流も進んでいる様子もうかがわれた。
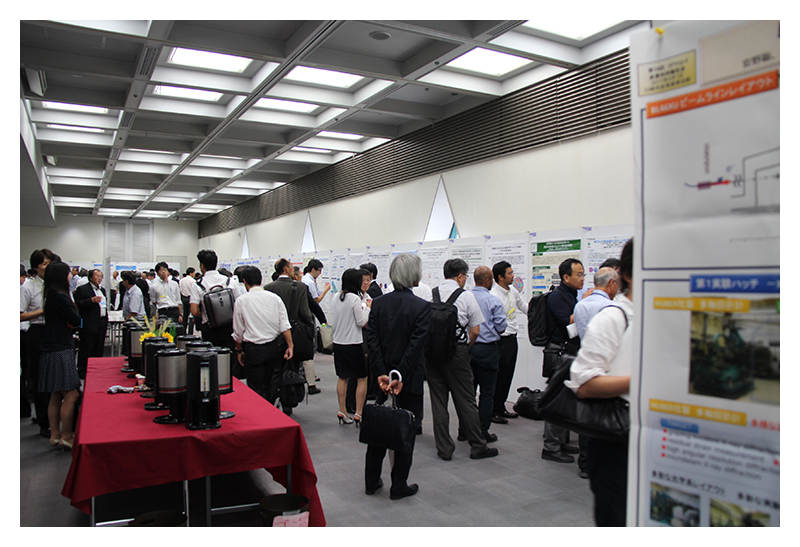
図3 ポスター会場の様子
6. おわりに
こうして本年の産業利用報告会が無事、盛況のうちに終えることができた。準備段階から当日の会場運営、さらに事後の取りまとめなど、主催5団体の事務局のご尽力と共催団体の関係者各位のご協力にこの場を借りて感謝の意を表したい。
(公財)高輝度光科学研究センター 産業利用推進室
〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1
TEL : 0791-58-0924
e-mail : msato@spring8.or.jp








