Volume 10, No.1 Pages 35 - 38
3. 研究会等報告/WORKSHOP AND COMMITTEE REPORT
3rd International Workshop on Radiation Safety of Synchrotron Radiation Sources (Radsynch’04)
日本原子力研究所 放射光科学研究センター/(財)高輝度光科学研究センター Synchrotron Radiation Research Center, JAERI / JASRI
放射光施設の放射線安全に係る国際ワークショップ(Radsynch’04)が11月17日から19日の3日間、SPring-8の普及棟で日本原子力研究所、(独)理化学研究所、(財)高輝度光科学研究センターの共同主催で開催されました。このワークショップはAPS、ESRF、SPring-8の3極研究協力協定に基づき、毎年開催されている3極会議のテーマ別ワークショップの位置づけとして、今回で3回目となります。このワークショップは第3世代大型放射光施設、APS、ESRF、SPring-8の建設も一段落し、順調な稼動を行っているときに、また多くの第3世代中型放射光施設の建設が計画されていたときに、放射光施設の抱える放射線安全や放射線挙動を討議する世界的な規模の場を設けてほしいとの要請をうけて、P.K.Job(APS)、P.Berkvens(ESRF)、と筆者が相談し、2001年4月にAPSで開催したのが始まりです。このワークショップは小さいながらも放射光施設の放射線安全・挙動を世界規模で議論できる唯一の会議であり、参加者の多くから是非継続してほしいとの要請を受け、2002年10月に第2回ワークショップがESRFで開催されました。このときの様子は放射光学会誌第16巻第2号に詳しく報告されています。今回は3回目であり、しかもアジアで開催することから、このワークショップの目的である「放射光に係る放射線物理・放射線工学研究の成果を広く公開、討議することを通じて放射光施設の放射線安全、遮蔽設計技術の向上を図るとともに放射光科学の発展に寄与する」ことに加え、アジアからの参加を出来るだけ働きかけること、次世代放射光施設計画やTop-up運転を主テーマの1つとすること、議論を重視した会議運営にすることなどを目標にしました。その結果、70名を越える方の参加があり、そのうちの半数近くが国外からの参加者(10カ国29名)という、この種の会議としては珍しいこととなりました。以下に参加機関を示します。アジアからは日本を含めて5カ国8施設1大学の参加でした。
Advanced Photon Research Center(APRC/JAERI), Japan
Berthold Technologies GmbH&Co KG, Germany
Berliner Elektroenspeicherring-gesellschaft fuer Synchrotronstrahlung (BESSY), Germany
Canadian Light Source (CLS), Canada
Daresbury laboratory (Daresbury), UK
Deutsches Elecktronen Synchrotron (DESY), Germany
Diamond Laboratory (DIAMOND), UK
Duke University, USA
European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), France
High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Japan
Institute for Synchrotron Radiation (ANKA), Germany
Institute of High Energy Physics (IHEP), P.R.China
Japan Synchrotron Radiation Research Institute (SPring-8
/JASRI), Japan
Japan Atomic Energy Research Institute (SPring-8/JAERI), Japan
Joint Institute of Nuclear Research (JINR), Russia
Korea Institute of Nuclear Safety (KINS), Korea
National Synchrotron Light Source, Brookhaven National Laboratory (NSLS), USA
National Synchrotron Radiation Research Center (NSRRC), Taiwan
Nagoya University, Japan
Pohang Accelerator Laboratory (PAL), Korea
Shanghai Synchrotron Radiation Facility (SSRF), P.R.China
Singapore Synchrotron Light Source (SSLS), Singapore
Stanford Linear Accelerator Center (SLAC), USA
Synchrotron SOLEIL S.C. (SOLEIL), France
The institute of Physical and Chemical Research (SPring-8 /RIKEN), Japan
University of Hyogo (NewSubaru), Japan
Yale University, USA
ワークショップは(財)高輝度光科学研究センター、吉良理事長の開会挨拶で始まり、その後、まず参加者の自己紹介からはじめていただきました。議論を活発にする狙いで行ったのですが、場を和ませるのに大いに効果があったように思います。ワークショップでは7つのカテゴリー、合計37件の口頭発表がありました。全て厳密に7項目に分類できるものではありませんが、各々放射光施設放射線物理・安全に関連する(1)コミッショニング状況も含めた施設の現状報告、(2)トップアップ運転、(3)新施設やアップグレードを含めた施設設計、(4)誘導放射能を含めた放射線測定、(5)放射線損傷、(6)遮蔽設計・解析手法、(7)次世代放射光施設、です。そのほかに特別に討議時間を3回ほど設けました。以下にその概略を示します。
まず(1)の施設現状報告では高エネルギー加速器研究機構の電子加速器群の現状と問題点の抽出、放射化した廃棄物の再利用に向けた取り組みなどの報告、カナダ放射光施設CLSのコミッショニング時における施設周辺での放射線線量分布、英国DIAMOND施設の建設状況、シンガポール放射光施設SSLSの現状が報告されました。これらは施設の現状認識と問題点の把握に有用であり、地味ではありますが今後のワークショップの1つのテーマとして引き続き取り上げるべきと思われます。(2)トップアップ運転に係る事項ではNSRRCやBESSY、Duke大学のシミュレーション計算結果、およびSPring-8のシミュレーション計算と中性子線量測定結果が報告されました。今後益々蓄積電子ビームの低エミッタンス化が図られる中で問題となる蓄積電子の短寿命化を補う点からもトップアップ運転が必要とされます。これらはこのトップアップ運転を安全に遂行するために必要不可欠な技術であることから関心を集め、時期を得たテーマであったと思います。次に(3)新施設やアップグレードを含めた施設設計では上海放射光施設、北京高エネルギー物理学研究所BEPC II計画、SLAC,SPEAR 3アップグレード計画に関して、実際の施設遮蔽設計やアップグレードする際の問題点等についての報告・議論がありました。また、ALS、APS、NSLS、SSRLとSPring-8の加速器およびビームラインに関する遮蔽安全設計思想と実際に関しての詳細な比較がSLACから、また同様にESRF、Daresbury、DIAMOND、とSOLEILの比較がESRFから報告されました。これらは今後の新施設設計やアップグレードに大いに役に立つデータと思われます。(4)誘導放射能を含めた放射線測定では、New SubaruとKEKから光核反応中性子の測定と逆コンプトン電子光を用いた実験計画、およびシミュレーション計算結果について報告されました。これらは放射光施設のような電子加速器施設設計の基礎データとしても重要であり、更なる発展が望まれます。また、Berhold社からANKAに導入予定の高エネルギー中性子に高感度をもつ中性子モニターの原理とCERNでの校正結果の報告、気泡検出器(superheated emulsion drop detector、通称バブル検出器)を用いた中性子スペクトルの測定原理の概説と放射光施設への応用がYale大学とESRFから報告された。この気泡検出器を用いた中性子スペクトル測定は検出器が小さく取り扱いが簡単等、大いに興味のあるところですが、再現性の問題等、改良の余地があるように思います。(5)放射線損傷ではSPring-8から4件の報告、1つは加速器運転開始から今までに放射線によると思われる損傷の程度とガフクロミックフィルムを用いた加速器周辺の積算線量測定、1つは放射光を用いたガフクロミックフィルムの校正とトラック検出器(CR39)を用いた加速器周辺の中性子測定結果、1つは電子線を用いた挿入装置用磁石の減磁実験結果、および信号ケーブルの過剰放射線暴露による誤動作とその対策についてです。これらは各々放射光施設として重要な問題ばかりですが、その中でも真空計等の過剰放射線による誤作動の問題とそれを解決するための信号ケーブルの改良などに関心が集まっていました。次に(6)遮蔽設計・解析手法ですがCLSからEGS4モンテカルロ計算によるガス制動放射線の散乱分布評価結果の報告、SPring-8からは3GeVと8GeV施設の比較から、放射光ビームライン遮蔽での再生効果の現れ方の違いや分岐ビームラインの2回散乱光子の重要性、ガス制動放射線分布の相違などの報告を行いました。これらは中型施設に重要な情報を与えるものです。(7)次世代放射光施設では、世界中のほとんどのX-FEL やERL計画、合計6施設(NSLS-II、DELSY、SCSS、PAL-XFEL、Daresbury-ERLP、TESLA、LCLS)の報告がありました。これらは実際に計画が進行中のもの、予算が認可されたものなど、それぞれ各段階にありますが皆精力的に遮蔽設計・安全解析を実施している様子が伺われ、また、これだけの次世代施設計画を一度に勉強できたことは幸いでした。
このワークショップの運営方針の1つに議論を出来るだけ重視することを心がけました。そのための仕掛けをいくつか採用しました。その1つは人数が多少、多かったけれども会議を円卓形式とし、お互いの顔が見えるように、かつ席をあらかじめ決めておくことにしました(会議中の写真を参考にしてください)。これは私がほとんどの参加者と面識があり、相手を理解していたからかもしれませんが、概ね成功だったようです。もう1つは会議中、議論のための特別な時間を数回に分けて設けたことです。限られた期間の中で十分な時間をとることが出来ませんでしたが、夕食後も議論する場を提供するなど、出来る限り便宜を図りました。その場で議論されたことは設計・評価手法に関する国際協力の可能性についてです。前段の(3)施設設計で若干触れましたが、今回かなり詳細な施設設計思想や安全思想、実際の設計などが日米5施設、欧州4施設間の比較データとして提示されました。これをもっと多くの施設に拡大してデータの充実を図ることや施設設計にコンセンサスが得られるかどうか、かなり白熱した議論がなされました。結論を申しますと、施設間の比較データは非常に有用であるけれども、施設設計思想や実際の設計に際してコンセンサスを得ることは困難であると思われる。しかしながら今後も情報交換や意見交換は積極的に行うことが必要である、ということでした。このことは当然の結論のようにも見えますが、情報交換や意見交換を積極的に行うことを確認できたことは大きな成果と思います。そのほかに、このワークショップ組織委員会の枠組みを保持すること、ワークショップのプロシーディングスを作成すること、Journal of Radiation Measurementsの特集号として出版するようにとの申し出を受けること、次回、4th Radsynchワークショップは2006年後半から2007年前半にCanadian Light Source かBrookhaven National Laboratoryで開催することを想定し、最終的に組織委員会で次回開催場所及び時期について決定することなどが確認されました。
このワークショップのもう1つの大きな特徴は、SPring-8で開催した会議で企業展示を初めて比較的大掛かりに行ったことです。検出器・線量計関係の10社に協賛していただきました。これはもちろん資金的な問題もありましたけれども、出来るだけ企業の方に負担をかけずに世界中の放射光施設安全設計責任者等が一同に会するこの機会に、特に多くの中規模放射光施設の建設が進行しているこの時期に、日本の検出器・線量計関係企業およびその製品を知ってもらう機会を提供することを意図しました。あまり展示見物に時間を割くことは出来ませんでしたが、それでも多くの参加者が興味を持って熱心に展示物を見ている姿が見られ、ある程度目的は達成されたものと思っています。
比較的評判の良かったワークショップポスターとワークショップの様子、立食パーテイー、および企業展示の様子を写した写真を掲載させていただきました。少しでもその雰囲気を味わっていただけたらと思います。ポスターは私が慌てて作成したもので、風景写真も自分のアルバムから気に入ったものを使わせていただきました。さてその場所は私が最も好きな場所の1つで、日本を代表する庭園です。本ワークショップに関する情報、プログラム、および発表に使用したパワーポイントファイル等は以下のURLアドレスで見ることが出来ます。
http://radsynch04.spring8.or.jp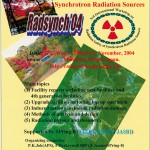
ワークショップポスター
Radsynch ’04 Buffet Party
ワークショップの様子
企業展示の様子
最後に、ワークショップ終了後、多くの参加者から会議運営について賞賛のメールをいただきました。これも現地実行委員の方々、KEKの伴氏を始め、兵庫県立大の宮本氏、SPring-8/RIKENの石川氏、SPring-8/JASRIの下村氏、多田、成山両氏それから特に高城君、谷口両君および事務局の當眞さんの協力の賜物です。また施設見学に協力していただいた、JASRI加速器部門およびビームライン部門の方々、それから原研事務の中山さん、杉山さんには煩雑な事務手続きを処理していただきました。この場を借りてお礼申し上げます。
浅野 芳裕 ASANO Yoshihiro
日本原子力研究所 放射光科学研究センター
兼(財)高輝度光科学研究センター
〒679-5148 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1
TEL:0791-58-0802, ex6311 FAX:0791-58-2740
e-mail:asano@spring8.or.jp








