Volume 04, No.1 Pages 48 - 49
6. 談話室・ユーザー便り/OPEN HOUSE・A LETTER FROM SPring-8 USERS
トライやる・ウィーク奮闘記(中学生が地域に学ぶ体験活動週間「トライやる・ウィーク」について)
After the Take Care of the Learning by Experience “Try-yaru Week”
日本原子力研究所 関西研究所 放射光利用研究部 Dept. of Synchrotron Radiation Facilities, JAERI Kansai Research Establishment
SPring-8のある兵庫県では、神戸の震災や須磨の少年事件等での教訓をもとに、兵庫県教育委員会が中心になり県下全中学2年生を対象に、「トライやる・ウィーク」事業というものを計画した。本事業は、中学生が地域等に学ぶ体験活動週間であり、普段の学校ではできないことや、やってみたいことを学校を離れて体験してみるものである。例えばコンビニやスーパーで働く、保育園で子供の世話をする、お年寄りの介護を手伝うなど、生徒一人ひとりが自立性を高め、将来にたくましく「生きる力」を育むことを目指す1週間である。
この体験活動の推進に当たり、SPring-8の地元3町の教育委員会からも中学生の受入依頼があった。原研・理研・(財)高輝度光科学研究センターでは積極的に中学生を受け入れ、対応は職員がボランティアという形で中学生を指導することとした。
学校側の要請としては、本活動では特別なプログラムを組むことなく、普段の仕事の中で中学生を働かせ、「仕事とはこういうものだ」ということを体験させてほしいとのことである。しかし、コンビニやスーパーでの活動と異なり、SPring-8では中学生を対象にした仕事を見つけることは非常に困難であった。ボランティアの職員達はそれでもなんとか一生懸命準備をして、中学生に有意義な体験をしてもらえるよう体制を整えた。
そして、平成10年11月9日(月)~13日(金)の5日間、午前9時から午後3時まで中学生をSPring-8に受け入れ、「トライやる・ウィーク」が実施された。SPring-8での体験を希望する中学生は、地元の3つの中学校から合計22名(女子8名、男子14名)であったが、実は受入側のSPring-8では、対応したボランティアの職員は中学生の数を上回り30名以上になるほど難しい活動であった。
SPring-8での「トライやる・ウィーク」は、全体の仕事を理解してもらうことを主目的にした。すなわちSPring-8は研究だけやっている施設ではなく、多くの人々が、いろいろな仕事を協力して行うことで成り立っているのだと言うことを理解してもらえるよう努めた。そして参加中学生を5~6名づつの班に分け、班毎にSPring-8で関連する各種の業務をローテーションで体験させた。

もくもくと作業に取り組む(若干さぼり気味の人もいるけど…)
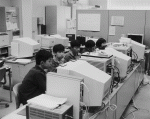
入射系機器制御室で、機器運転操作の実習
業務は大きく2つに分けられる。まずいわゆる研究部門として、加速器の研究開発業務を線型加速器及びマシン実験棟で体験した。但し研究開発といっても地道な作業の積み重ねであり、それこそボルトを締めること、線を繋ぐこと、ヤスリをかけることなどから体験してもらった。また、利用系開発部門ではビームラインの真空リークテストにチャレンジし、基本的なことがしっかりできていないと、決して実のある研究が出来ないのだと言うことを理解してもらうようにした。このような仕事は、華やかな研究と、それに携わるいつも白衣を着ているような研究者・科学者をイメージしていた中学生には、ちょっと驚きだったかもしれない。
もう一つの業務は研究支援である。例えば電気・水といったユーティリティー施設の管理がしっかり行われなければ、どんな装置も動かないこと。また事務的な支援業務がなければ、利用者への対応や物品の契約なども進まず、優れた研究も出来ないことを理解してもらえれば、と考えた。
また、最終日(金曜日)には、4日間の業務体験をパソコンやデジカメを使ってレポートにまとめる作業も行った。

インターネットを使って情報を見つけだす(広報室にて)
さて、5日間の「トライやる・ウィーク」を通じて、我々ボランティアはできるだけ充実した体験をしてもらおうと、内容をいろいろ工夫して精一杯対応したつもりであったが、その時々の中学生の反応は今ひとつのように思われた。
しかし、最終日にまとめた体験レポートで、「おもしろかった」とか「仕事が大変なことがよく解った」などと書かれているのを見ると、彼らも心の中ではいろいろと反応していたのだなと感じた。見たこともないSPring-8のような施設に来て、職員たちにどう対応していいものかわからず、かなり緊張していたのかもしれない。そして今までにない体験と、身近にはいない研究者や技術者に囲まれながら、彼らは彼らなりに精一杯背伸びしてがんばっていた様子がうかがわれる。
この「トライやる・ウィーク」は今年初めて行われる試みであり、参加する方も受け入れる方も手探りの状態であった。お互い緊張し合っていたのは仕方ないことだと思う。しかし、来年以降も継続して行われるのであれば、今後我々も中学生の心をノックできるような親しみやすくわかりやすい魅力的なアプローチを、更に検討していく必要があることを強く感じた。この「トライやる・ウィーク」の1週間は、中学生だけでなく我々にとっても改めて「仕事」や「協調」というものを視点を変えて考え直すよい機会であったと思う。
鈴木 國弘 SUZUKI Kunihiro
日本原子力研究所 関西研究所 放射光利用研究部
〒679-5143 兵庫県佐用郡三日月町三原323-3
TEL:07915-8-0866 FAX:07915-8-0311
e-mail:kuni@haru01.spring8.or.jp








