Volume 30, No.1 Pages 47 - 50
2. 研究会等報告/WORKSHOP AND COMMITTEE REPORT
フロンティアソフトマター開発専用ビームライン産学連合体 第14回研究発表会
The 14th Conference on Consortium of Advanced Softmaterial Beamline (FSBL)
[1]フロンティアソフトマター開発専用ビームライン産学連合体 代表 Advanced Softmaterial Beamline (FSBL)、[2]同 運営委員長 Advanced Softmaterial Beamline (FSBL)、[3]同 運営副委員長・広報委員 Advanced Softmaterial Beamline (FSBL)
1. はじめに
フロンティアソフトマター開発専用ビームライン産学連合体(FSBL)は第14回研究発表会を2025年1月14日~15日の2日間に亘り、アリストンホテル神戸16F(バルセロナ)およびZoomのハイブリッド形式にて開催した。
FSBLは、ソフトマターの分野で日本を代表する企業と大学によって、放射光利用によるソフトマターの研究開発の発展を目指して結成された連合体である。(国研)理化学研究所と(公財)高輝度光科学研究センターの多大なご協力のもと大型放射光施設SPring-8のBL03XUに、日本で初めてのソフトマター研究開発専用ビームラインが設置された。2010年4月より供用を開始し、2019年に9月に第1期の活動を終了した。現在、FSBLは2019年10月より第2期となり、その最後の年となる。2025年度は第3期がスタートとなり今後も活動を続けていく。これらの活動により創出された研究成果を、広く一般に発表するとともに、参加メンバー間での情報を共有し、さらに効果的かつ高度な成果を輩出するため、年に1回研究発表会を開催している。
昨年に引き続き、全15グループの研究発表を2日間での開催で行った。また、最新の高速・積分型検出器CITIUSに関する特別講演、SPring-8を活用した高分子構造解析に関する特別講演をそれぞれ実施した。以下にその概要を示す。
2. 開会の挨拶
FSBL代表 小池淳一郎(DIC株式会社)より、研究発表会の開会が宣言され、4名の来賓よりご挨拶を頂戴した。
まず、文部科学省 科学技術・学術政策局 研究環境課の野田浩絵課長より、NanoTerasuの運用が開始されたことに触れ、今後ますます官民パートナーシップを活用して産学連携を推進し、さらにはSPring-8-IIとの相補的利用や利用者層の拡大が進むことへの期待が述べられた。続いて、(国研)理化学研究所 放射光科学研究センターの矢橋牧名グループディレクター(石川センター長代理)から、SPring-8-IIのアップグレードを見据え、放射光施設のポートフォリオを基にユーザー目線での展開への期待が語られた。また、2025年度から始まるFSBL第3期の新しい運営体制の下で、社会に対してインパクトのある活動への期待が語られた。さらに、(公財)高輝度光科学研究センターの雨宮慶幸理事長からは、FSBL設立初期のプレーヤーとしての活動を振り返り、後半には施設側からFSBLを通じて産学連携の先駆者としての役割を果たしてきたことが述べられた。第3期に向けて、専用ビームラインから理研ビームラインへの移行とともに、世代交代によるさらなる活性化が期待されるとのメッセージがあった。最後に、FSBL企画戦略アドバイザーで(一社)光科学イノベーションセンターの高田昌樹理事長から、プラスチックの強化、資源化、循環化における放射光の重要な役割について言及された。NanoTerasuやSPring-8-IIを評価拠点とした活動、そして産学連携体としての更なる発展が期待されている旨のご挨拶があった。引き続きFSBL運営委員会委員長 秋葉勇(北九州市立大学)より、FSBLの概要、沿革、最近の活動についての紹介が行われた。これまでの活動をベースに、2025年度からの第3期FSBLへ向けて、さらに発展的な活動をするため、メンバー一丸となって取り組む決意が述べられた。
3. 講演会第1部
FSBL副代表の船城健一(東洋紡株式会社)を座長として、研究発表会・講演会第1部が開始された。まず、特別講演として、(国研)理化学研究所 放射光科学研究センターの初井宇記先生から「次世代X線画像検出器CITIUSとそのデータ解析」についてご講演いただいた。ご講演では、CITIUS検出器の計測原理に始まり、超高ダイナミックレンジなど新しい機能、データ処理方法、そして、そして実験での活用例を交えた内容についての報告があり、FSBLでの活用に対する期待が高まった。引き続き、デンソーグループより「X線光子相関分光法による延伸条件下における熱可塑性高分子のダイナミクス評価」、そして三菱ケミカルグループより「リオトロピッククロモニック液晶(LCLC)の乾燥過程における構造形成機構解析」についての報告が行われた。
4. 講演会第2部
FSBL広報委員の蟹江澄志(東北大学)を座長として、「SPring-8-IIについて」というテーマで、理化学研究所 放射光科学研究センターの矢橋牧名先生からSPring-8-II高度化プロジェクトに関する講演が行われた。このプロジェクトは、第4世代放射光源として硬X線領域で世界最高クラスの輝度と安定性を実現しつつ、施設全体の大幅なグリーン化を推進することを目指している。2027年度後半から1年間のシャットダウン期間を経て、2029年度からの利用運転開始が予定されている。矢橋先生は、この「未来予測の科学」の基盤を築く本プロジェクトの進捗状況と今後の計画について紹介された。引き続き、4つのFSBLメンバーより、研究発表が行われた。横浜ゴムグループより「時分割超小角X線散乱法を用いたSBR中silicaの分散状態に関する研究」、東レグループより「オートエンコーダーを用いた時分割小角X線散乱の解析」、住友ベークライトグループ「触媒硬化型エポキシ樹脂の架橋ネットワーク構造形成メカニズムの解析」、帝人グループ「X線光子相関分光法によるウレア系硬化剤を含むエポキシ樹脂のダイナミクス評価」の報告が行われた。
研究発表会第1日目のプログラムは以上となり、FSBL学術諮問委員長 金谷利治先生(京都大学名誉教授)より、FSBLの将来への発展を祈念する旨閉会のご挨拶を頂戴し、FSBL運営副委員長 藤原明比古(関西学院大学)より1日目の閉会の言葉をいただいた。

写真1 特別講演① 初井宇記先生

写真2 FSBLメンバーの発表(東レグループ)
5. 懇親会
1日目のプログラム終了後、アリストンホテル神戸(15Fアンダルシア)で懇親会を開催した。38名の参加者となり、FSBLメンバー間のみならず、施設側の参加者との交流も活発に行うことができた。

写真3 懇親会
6. 講演会第3部
研究発表会2日目は、FSBL運営委員長 秋葉勇(北九州市立大)より開会の宣言を行い、講演会第3部からスタートした。
広報委員 西辻祥太郎(山形大学)を座長とし、DICグループより、「電解質存在下における乳化剤ミセルの構造評価」、先進研究を目指すプログラムであるアドバンスビームタイム利用課題成果発表として竹中幹人先生(京都大学 化学研究所)より「SAXSによる高せん断下における溶媒中の高分子鎖の変形の可視化」、住友ゴムグループより「USWAXS-CT法を用いたフィラー充填ゴムの一軸延伸下でのフィラーと分子鎖の配向分布評価」、クラレグループより「水/グリセロール混合分散媒中の親水性フュームドシリカの粒子凝集状態とせん断増粘挙動」について報告が行われた。
休憩をはさんだ後、特別講演として、神戸大学大学院工学研究科の西野孝教授から「SPring-8で調べた高分子力学物性」というテーマでご講演をいただいた。ご講演では、SPring-8を利用するきっかけや研究の歴史について触れ、特にマイクロビームX線回折を用いて異種高分子界面の構造と接着性の相関解明を目指す研究、分子鎖軸方向の結晶弾性率の評価、単繊維を用いた回折実験などについて紹介された。また、SPring-8の工事着工から現在に至るまでの30年にわたる研究の歩みも振り返られた。

写真4 特別講演会② 西野孝教授
7. 講演会第4部
広報委員 鳥飼直哉(三重大学)を座長とし、旭化成グループより「高分子微粒子フィルムの力学特性とナノスケール構造の相関」、三井化学グループより「コントラスト変調小角X線散乱による結晶構造と架橋網目構造の分離解析」、東洋紡グループより「SAXS-CT法を用いたUHPE繊維内部のナノスケール構造分布評価」の報告が行われた。
8. ポスター発表
FSBLメンバー15社より16件のポスター発表による報告が行われた。ポスター発表は現地会場でのみの実施とし、発表者は2組に分かれ、ポスター発表時間を前半と後半に分けて開催した。
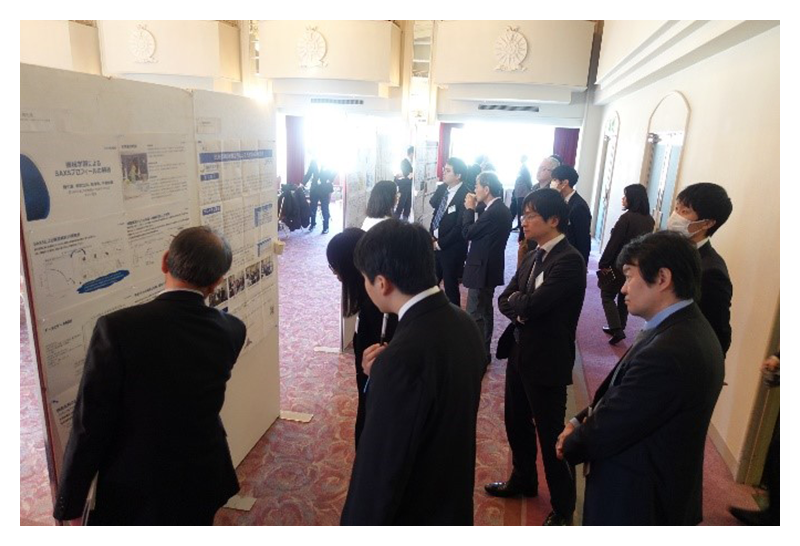
写真5 ポスター発表
9. 講演会第5部
引き続き、FSBL広報委員 山本勝宏(名古屋工業大学)を座長とし、関西学院大学グループより「マイクロビームX線を用いたヒト毛髪内の水の動きの分析手法の開発」、住友化学グループより「角度分解X線散乱を用いたポリオレフィンフィルムの三次元構造解析」の報告が行われた。
以上を以て、すべての発表が終了した。
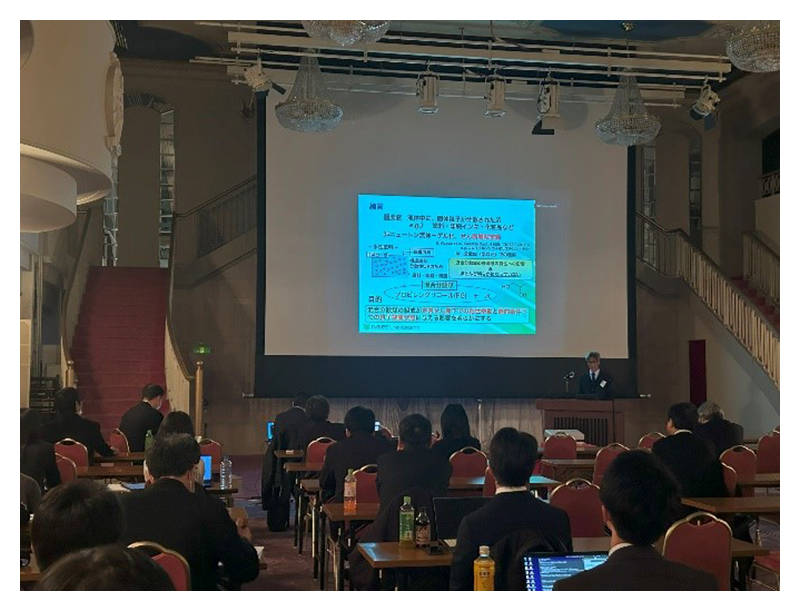
写真6 FSBLメンバーの発表(クラレグループ)
10. 総括
FSBL堀江賞選定委員会・産学連携将来高度化委員長田代孝二(豊田工業大学名誉教授)より、いくつか提言をいただいた。田代委員長は、研究者として最も重要な視点を見失わず、基本に立ち返って真摯に研究に取り組むべきであると述べられた。また、メンバー同士で議論を交わし、新しい研究テーマを創出することが重要だと強調された。引き続きFSBLが活発に活動を進め、多くの成果を生み出すことを祈念するという総括の言葉をいただいた。
11. 閉会の挨拶
FSBL学術諮問委員の西敏夫(東京大学・東京工業大学名誉教授)から、強い日本を取り戻すためには、材料開発においてコストダウンではなく、付加価値を高める視点で取り組むべきだという提言があった。また、高付加価値材料の創出において、FSBLや放射光施設をますます活用していくことを期待する旨、閉会の挨拶をいただいた。
12. まとめ
今回は、第2期の最終年度であり、その集大成と新たな出発を意味して、FSBL発足時の第1回開催に倣い、2回目の大学外での研究発表会の開催となった。今回もハイブリッド形式で実施され、現地参加者53名、オンライン参加者85名、合計138名が参加し、FSBLの活動を広く報告することができた。懇親会を通じて、FSBLメンバー間での情報交換や、施設側(理研)との今後の活動についての意見交換も行われた。
謝辞
FSBL第14回研究発表会は、下記の14団体より協賛をいただいた。深く感謝申し上げる次第である。
・(国研)理化学研究所 放射光科学研究センター
・(公財)高輝度光科学研究センター
・(一財)光科学イノベーションセンター
・(一財)総合科学研究機構 中性子科学センター
・(公社)高分子学会
・(一社)繊維学会
・(一社)日本ゴム協会
・(公社)日本化学会
・日本中性子科学会
・日本放射光学会
・産業用専用ビームライン建設利用共同体(サンビーム共同体)
・京都大学産官学連携本部電気自動車用革新型蓄電池開発(京大ビームライン)
・(株)豊田中央研究所(豊田ビームライン)
・(公財)ひょうご科学技術協会(兵庫県ビームライン)
フロンティアソフトマター開発専用ビームライン産学連合体
〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1
e-mail : fsbl-office@fsbl-spring8.org








