Volume 29, No.2 Pages 108 - 110
2. 研究会等報告/WORKSHOP AND COMMITTEE REPORT
SACLA Users’ Meeting 2024
[1](公財)高輝度光科学研究センター XFEL利用研究推進室 XFEL Utilization Division, JASRI、[2](国)理化学研究所 利用システム開発研究部門 Advanced Photon Technology Division, RIKEN SPring-8 Center
1. はじめに
2024年3月11日および12日の2日間にわたり、SACLA Users' Meeting 2024が開催された。近年はCOVID-19の影響によりオンラインでの開催が続いていたが、今年度は4年ぶりの対面形式による開催となり、国内外の大学や研究機関から約90名に参加いただいた。2日間の会議を通して、最新のSACLAの性能に関する情報共有やXFEL利用研究の将来のあり方について、施設と利用者および利用者同士での活発な議論が行われた。

写真1 集合写真
2. 会議の内容
まず、石川哲也RSCセンター長および米田仁紀教授(電気通信大学、SPRUC XFEL利用研究会代表)による開会挨拶をもって、本年のミーティングがスタートした。まず初めに行われた“Facility Session”では、SPring-8/SACLAを取り巻く国内外の情勢や、SACLAの利用研究や硬X線FELビームライン(BL2・BL3)、軟X線FELビームライン(BL1)、光学レーザー、ハイパワー光学レーザーそしてX線検出器高度化の現状について概要が報告された。
続いて、“High-intensity X-ray Science”と題する特別セッションが開催された。他のXFEL施設とは一線を画するSACLAの特徴の一つとして、精密なXFELのナノ集光技術に基づく、高強度X線が挙げられる。本セッションは、近年発展を遂げている高強度X線を利用したサイエンスを紹介し、利用の拡大を図るために企画された。本セッションはイントロダクションと3つの講演から構成されていた。まず、イントロダクションとして、井上伊知郎博士(理化学研究所)からセッションの趣旨説明、講演者の紹介、SACLAにおけるナノ集光装置の紹介がなされた。次に、山田純平助教(大阪大)から、最近達成されたXFELの7 nm集光とその応用について報告があった。1022 W/cm2に達する高強度XFELを照射されたクロム原子はその束縛電子を全て失い、完全電離状態になることが示された。ただし、その電離プロセスは非常に複雑であり、全てを解明するためには理論モデルやシミュレーションが必要であるとの議論が交わされた。
次に、Zain Abhari氏(University of Wisconsin-Madison、USA)から、高強度XFEL照射によって励起されるKα線レーザーとその応用に関する講演が行われた。これは、高強度XFEL照射によって物質中に反転分布が形成され、そこから放射されるKα線がレーザー発振するという現象である。このKαレーザーの増幅機構を基にしたX-ray Laser Oscillator(XLO)の開発に関する議論が行われた。最後に、鈴木明大准教授(北海道大)から、コヒーレント回折イメージングに関する発表がなされた。産業界への応用例などの紹介とともに、単粒子イメージングへ向けての試料環境の開発状況などが議論された。いずれの発表もSACLAの独自性を活かした最先端の高強度XFEL利用成果であり、これまで馴染みのなかった参加者の興味を引き、利用の促進に繋がることが期待される。
次に、招待講演としてBo Iversen教授(Aarhus University、Denmark)の発表が、オンラインで行われた。タンパク質結晶構造解析で広く用いられているSerial femtosecond crystallography(SFX)を単位格子の小さい材料科学系試料に適用し、精密構造解析を行った結果が紹介された。材料科学におけるSFXの利用は今後の発展が期待されており、最新の研究成果の報告は非常に有意義であった。
第1日目の最後には、SACLA PRC委員長でもある米田仁紀教授より、課題審査委員会から利用者へ向けたメッセージが紹介された。
第2日目の午前中には、2023年度のSACLA/SPring-8基盤開発プログラムセッションが行われた。本セッションでは、2023年度に採択された提案課題のうち、「採択I」として研究開発予算の割り当てられた5つの提案について進捗報告が行われた。本山央人助教(東京大)からは、回転体ミラーによる2種類の軟X線集光装置開発と、回転体ミラーを組み合わせた軟X線顕微鏡の開発に関する報告があった。宮脇淳博士(量子科学技術研究開発機構)からは、広ダイナミックレンジ・高速読出し軟X線用CMOS検出器の開発状況について報告がなされた。南後恵理子教授(東北大)を含む研究グループでは複数の構造生物学実験プラットフォームや実験技術の開発が並行して進められているが、本会議ではその中でも、二液混合による反応励起手法や、カプトンテープによる試料搬送装置の開発状況の報告がなされた。また、池田暁彦助教(電気通信大)からは、100テスラに達する超強磁場発生装置PINK02の開発状況とSACLAでの実験結果が報告された。昨年度のPINK01では、XFEL施設としては世界最高レベルとなる77テスラの磁場強度が報告されたが、本年度はその記録を更新する形となった。続いて尾崎典雅准教授(大阪大)の講演では、凝縮系物質などにおける磁化過程の観測に向けた、ハイパワーレーザーと高強度磁場発生装置を組み合わせた実験プラットフォームについての報告があった。いずれの採択課題においても、他のXFEL施設では類を見ないSACLA独自の実験基盤装置の開発が進められている。今後もSACLAがユニークな研究成果を創出し続けていくためには、本プログラムによって施設側と利用者側が密に連携しSACLAの機能を最大限に引き出すことが必須である。本プログラムは毎年度12月から1月ごろに募集が行われているので、ぜひ皆様の積極的な応募をお願いしたい。
第2日目午後にはブレイクアウトセッションとして、SACLA/SPring-8基盤開発プログラムにて整備が進められている共用装置について、それぞれの開発状況を利用者と共有し、今後の研究展開を議論する2つのセッションが同時並行で開催された。セッションAはポータブル強磁場発生装置(PINK)とSACLAを組み合わせた研究に関するセッションで、PINKの開発に携わっている池田暁彦助教から最新の研究成果に加え、木原工准教授(岡山大)から、ホイスラー合金の研究紹介のほか、PINKを用いた今後の研究展開についての講演があった。また、野原実教授(広島大)からは、物質合成の視点からXFELとPINKを組み合わせた今後の研究に期待するテーマについての講演があった。その後、PINKを用いたXFEL実験で今後候補となりうる試料について議論が行われた。また、新しい実験手法として、強磁場環境下における磁気秩序を直接観測する磁気散乱法、電子状態変化を捉える分光法、ドメイン構造を検出するイメージングなどについて議論が行われた。セッションBでは、SACLAで開発中のポリイミドフィルムテープを用いた実験試料搬送装置について議論が行われた。現在主流である液体ジェットや高粘度媒体を用いた搬送方法と比較して、試料の消費量が抑えられることが特徴であることから、一度に大量の試料を用意することが難しい試料を用いる利用者から着目されている。初めに、南後恵理子教授(東北大)が、SACLAにおけるSFX実験用試料輸送方法について紹介し、テープによる試料搬送装置の開発に至った背景などの講演が行われた。続いて、藤原孝彰助教(東北大)とFangjia Luo博士(JASRI)から、本装置を用いた実証実験例の紹介があった。また、永野真吾教授(鳥取大)から、本装置を用いた簡易的な嫌気条件下でのSFX実験について紹介があった。セッションBでも、開発中の装置を用いた実験条件や、今後の展開などに関する議論が活発に行われた。
最後にポスターセッションについて報告しておく。対面形式での開催となったことにより、今回はポスターセッションの時間があらためて設けられた。施設報告だけでなく利用者からの報告など合計22件のポスターが掲示された。そしてポスターセッションの時間になると多くの参加者で賑わいを見せ、各所で活発な議論が行われ、対面形式での開催ならではの雰囲気があったように思う。
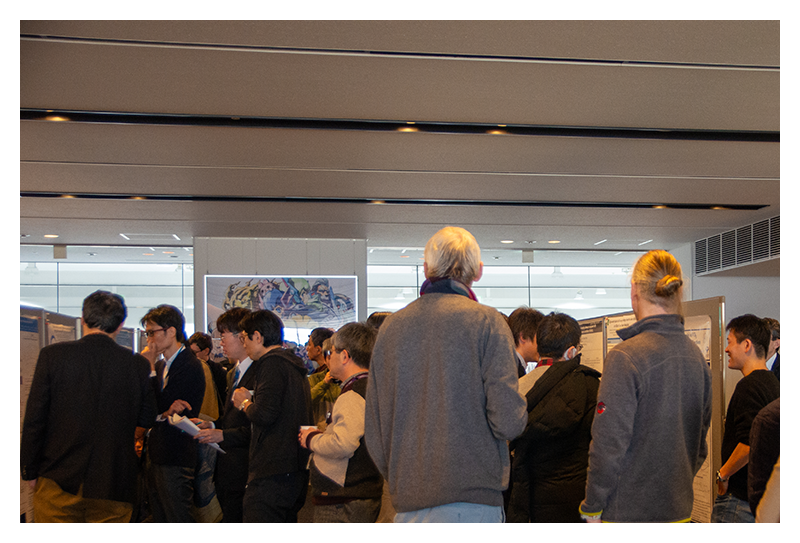
写真2 ポスターセッションの様子
3. まとめ
SACLA Users' Meetingは、利用者と施設および利用者間の情報共有と意見交換を主な目的として開催され、今回で通算9回目の開催となる。本ミーティングでの利用者からの要望に対する施設側の対応や、施設側からの情報を活かしたSACLA利用研究の展開などの情報はホームページ等で随時公開される予定である。今後もSACLA Users' Meetingは開催される予定となっている。次回の開催ついては詳細が決まり次第、SACLAのホームページ(http://xfel.riken.jp)などで情報が公開される予定である。
今回、各セッションにおける議論だけではなく、コーヒーブレイク中などでも各所で非常に活発な議論がなされていたのは、対面形式ならではの醍醐味である。今回のSACLA Users' Meetingも盛況のうちに終えることができたのも、国内外の多くの利用者の方々の参加と活発な議論をしていただいたことに尽きると思われる。ここにSACLA Users' Meeting 2024に関わった皆様に厚く御礼を申し上げる。
(公財)高輝度光科学研究センター XFEL利用研究推進室
〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1
TEL : 0791-58-0992
e-mail : osigeki@spring8.or.jp
(公財)高輝度光科学研究センター XFEL利用研究推進室
〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1
TEL : 0791-58-0992
e-mail : inubushii@spring8.or.jp
(公財)高輝度光科学研究センター XFEL利用研究推進室
〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1
TEL : 0791-58-0992
e-mail : tono@spring8.or.jp
(国研)理化学研究所 利用システム開発研究部門
〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1
TEL : 0791-58-0802
e-mail : j.kang@spring8.or.jp
(国研)理化学研究所 利用システム開発研究部門
〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1
TEL : 0791-58-0802
e-mail : kubota@spring8.or.jp








