Volume 06, No.1 Pages 62 - 63
5. 研究会等報告/WORKSHOP AND COMMITTEE REPORT
国際ワークショップLEPS2000報告
International Workshop LEPS2000
[1](財)高輝度光科学研究センター 放射光研究所 加速器部門 JASRI Accelerator Division、[2](財)高輝度光科学研究センター 放射光研究所 ビームライン部門 JASRI Beamline Division、[3]大阪大学 核物理研究センター Research Center for Nuclear Physics, Osaka University
標記のワークショップは、大阪大学核物理研究センターとJASRIの共同主催により、2000年10月14日と15日の両日SPring-8で開催された。大阪で開かれた国際会議 SPIN2000のサテライトであり、海外からの9名を含め全体で約50名の参加者を得た。LEPS(Laser Electron Photons at SPring-8)はBL33LEP で得られるγ線を用いてクォーク-核物理を研究する施設で、既に2.4 GeVの偏極γ線の生成に成功し[1]、最初の物理実験の対象であるφ粒子の発生を確認している[2]。今回のワークショップは、このような成果を含めLEPSを内外に紹介し、将来の実験に向けてMeV-GeV領域の偏極γ線を用いた物理について議論するのが目的である。
第1日目の午前中は、BL33LEPの見学を行なった。レーザー(第一光学)ハッチ内の発振器と光学系(写真1)、実験(第二光学)ハッチ内のγ検出器(写真2)等の測定器類に関心が集まった。午後から第2日目にかけて18の講演がもたれた。一講演25分で、活発な議論が親しい雰囲気の中で行なわれた。
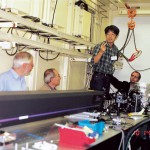
写真1 レーザーハッチ内部
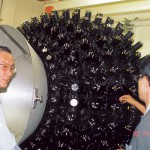
写真2 γ検出器
以下講演内容を概観する。上坪所長の開催の辞のあと、土岐(RCNP)は、QCDの閉込め機構に関する最近の理解が正しいならば、スピン-パリティが 0+ のグルーボールが1.5 GeV付近に存在するはずであり、もしそれがLEPSの偏極実験においてφ粒子生成への寄与として見つかれば、閉込め機構の解明につながるであろうと述べた。Hourany(IPN)は、GRAAL/ESRFの偏極光子と陽子標的によるηやnπ生成実験について述べ、散乱振幅の核子励起による理解の現状を示した。2001年にはγのエネルギーを1.5 GeVまで上げ、Σ粒子の生成を行なう予定が報告された。堀田(JAERI/SPring-8)はLEPSの最新の成果を報告したが、1 Tスペクトロメーターと3台のドリフトチェンバー及びTOFカウンターを組合せた測定系によるπ、K等の粒子識別は見事であり、LEPSがこの実験に有効なシステムを作り上げて、確かにφ粒子を見ているという印象を聴衆に与えた。Arestov(IHEP)は、ベクトル中間子の核子標的による小角度光生成について論じ、ヘリシティー振幅と偏極パラメーターの振舞いを運動学的におさえておくことの重要性を強調した。Wei(BNL)は、LEGS/BNLでの偏極HD標的の開発と、それを用いた中性子のスピン和則を調べる計画について話した。Wojtsekhowski(JLAB)は、ハドロンの弱い相互作用を調べることの意義について述べ、それによって生ずる重陽子中のP波成分を、JLAB/CEBAFで大強度(1015/s)の偏極γ線を発生させることによって検出するアイデアを提出した。笠木(東北大)は、東北大核理研のストレッチャーブースターリング蓄積ビーム中に挿入される内部標的からの1 GeVγ線を核標的に当ててη粒子生成を行い、原子核中の核子励起を調べることを提案した。また、そこで行える物理として、二重巨大共鳴の機構を調べることを挙げた。Krusche(Basel Univ.)は、MAMI/Maintzの855 MeV電子の制動輻射を用いた核内核子励起の研究について報告した。2001年にはエネルギーが1.5 GeVに上るそうである。これで一日目は終り、食堂でレセプションが開かれた。
2日目は、まず丸山(北里大)が、理化学研究所のRIBFに設置される予定の、MUSESの概念と現状を紹介した。嶋(理研)は、電総研での2〜30 MeVγ線による 4Heの光分解実験の結果を紹介し、107/sの強度をもつ、エネルギー分解能数%のγ線があれば、光核反応を10−2 の精度で測定することができ、核内での荷電対称性の破れやパリティ非保存過程に関する知見が得られることを指摘した。宇都宮(甲南大)は、電総研LEMPSからの数MeVγ線による光核反応実験を紹介し、γ線実験によって得られる天体核物理学的に重要な問題として、陽子過剰核や最も存在比の小さい180Taの宇宙における生成過程の解明、12C(α,γ)16O反応の断面積の決定等を挙げ、もし8 MeVの単色γ線が1013/sの強度で得られれば、この分野に飛躍的な進展がもたらされるだろうと述べた。Pietralla(Yale Univ.)は、光核反応の中性子閾値の直下に原子核の豊富な変形準位が横たわっていることを指摘し、106/keV/sの偏極γ線を用いた、パリティを含めた準位同定による「微細構造核物理学」の推進を提唱した。Zegers(JAERI)は、BL33LEPにおける分割型PWOカロリメーターを用いた蓄積リング内残留ガスによるBremsstrahlungの測定について報告し、水平方向のγ線分布が電子ビームの軌道と角度拡がりを正しく反映していること、また垂直方向分布の上下非対称性を用いて、リング内の電子ビームのスピン偏極を測定出来る可能性があることを示した。浜(東北大)は、赤外線自由電子レーザー(FEL)の世界の現状を紹介し、光学キャビティ中に溜った赤外線と電子の散乱で得られるγ線の性質について述べた。大垣(電総研)は、電総研LCS1におけるMeVγ線を用いた、Cr原子核の中性子閾値以下でのE1励起状態の確立とそのパリティの同定について報告し、LCS3計画について述べた。土橋(都立大)は、リニアコライダー用偏極陽電子源の開発の一環として、後方コンプトン散乱による大強度の偏極γ線生成を試験的に行なう装置をKEKのATFに設置したことの報告を行なった。宮原(JASRI)は、FELで得た赤外線をSPring-8の蓄積リングに導くことにより、大強度の10 MeV領域γ線を生成して核物理を行なうアイデアを提案した。有本(JASRI)は、SPring-8における10 MeV領域γ線生成のためのアルコール赤外レーザーの開発の現状について報告した。最後に、藤原(RCNP)がまとめを行なった。
今回のワークショップは、SPring-8をこの分野の研究者達に紹介するまたとない良い機会であったと思う。外部からの参加者の多くから、LEPSの計画立案から実験の立ち上げまでがいかにスムースであったかに驚いたと聞かされた。これもひとえに、SPring-8の運営サイドと放射光ユーザー諸氏の暖い御理解があったればこそである。この場をかりて、LEPS関係者一同、お礼を申し述べたい。
参考文献
[1]中野貴志、大橋裕二:SPring-8利用者情報Vol.4,No.5(1999)31.M.Fujiwara:"Studies in Quark Nuclear Physics at LEPS," in SPring-8 Research Frontiers 1998/1999.
[2]藤原 守:SPring-8利用者情報Vol.5,No.5(2000)266.
伊達 伸 DATE´ Schin
(財)高輝度光科学研究センター 放射光研究所 加速器部門
〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1
TEL:0791-58-0889 FAX:0791-58-0850
e-mail:schin@spring8.or.jp
豊川 秀訓 TOYOKAWA Hidenori
(財)高輝度光科学研究センター 放射光研究所 ビームライン部門
〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1
TEL:0791-58-1842 FAX:0791-58-1838
e-mail:toyokawa@spring8.or.jp
清水 肇 SHIMIZU Hajime
大阪大学 核物理研究センター
〒567-0047 茨木市美穂ヶ丘10-1
TEL:06-6879-8932 FAX:06-6879-8899
e-mail:hshimizu@rcnp.osaka-u.ac.jp








