Volume 04, No.1 Pages 7 - 10
2. SPring-8の現状/PRESENT STATUS OF SPring-8
線型加速器の改造について
Improvement of SPring-8 Linac
平成10年の夏期停止期間中に行った線型加速器の工事について、電子銃の改造とビームトランスポートライン(L3系、L4系)の建設を主眼において報告する。
1.はじめに
線型加速器は平成8年8月8日のファーストビーム以来、シンクロトロンへの入射器としての運転を継続してきた。新たにこの秋からのニュースバル蓄積リング(以下NSリング)への入射という使命を帯びることとなり、新規のビームトランスポートラインの建設及びNSリングへのビームパラメータに対応するための電子銃の改造を夏期停止期間に行った。その他、ビームの安定化を目的とした冷却水系の改造、クライストロン励振系の改造、モジュレーター系の調整などがあるが、ここでは割愛する。ちなみにここで言うビームトランスポートラインは電子ビームの輸送系のことである。
この夏は東北、北海道地方は連日の雨でとうとう梅雨明け宣言もなされないような異常気象であったが、SPring-8のある西播磨地区は、連日猛暑の続く、工事には過酷な気象条件であった。本来ならば、精密なアライメントの要求されるビームトランスポートラインは、建家が完成しコンクリートが落ち着いた状態で設置されるべきものであるが、本工事は種々の条件より、ビーム輸送トンネルの建設工事とかなりオーバーラップする工程となってしまった。そのため、ビームトランスポートラインの設置工事や電源の調整など空調の利かない状態で行うこととなり、かなりハードな工事であった。さらに、8月25、26日の原子力安全技術センターによる使用前検査に合格しなければ、線型加速器本体の運転が許可されないため、SPring-8全体の運転が停止してしまうというせっぱ詰まった状況であった。
しかし建設は何とかやり終えることができ、無事検査も合格し、予定通り線型加速器の運転を再開することができ、予定通り、NSリングへの入射も開始された。
2.電子銃の改造
線型加速器の設計当時は、陽電子ビームを蓄積リングに送り、イオントラッピングの影響をなくすことを想定していたため、陽電子発生用の大電流を発生させることが出来るような電子銃が製作、設置された。
しかし現在まで、電子の蓄積によってもイオントラッピングの効果による顕著な寿命の変化は観測されておらず、電子銃からは、100mA以下の小電流を引き出すという不安定な動作点での運転を行ってきた。電子の蓄積でも十分な寿命が得られているという判断により、小電流で安定な電子銃に変更することとなった。
この改造の目的は、グリッドエミッションと呼ばれる暗電流の低減を行い、また、口径の小さいカソードを用いることにより、より良いエミッタンスの電子ビームを引き出すということである。これは、ビーム電流を調整しやすくするということのほか、NSリングへの入射時のロスを少なくするという効果をもたらす。具体的には今までの大電流型の大口径カソードEIMAC社Y796から、小口径のカソードY845への変更を行い、電子銃の電場形状を決定するウェネルトの形状もそれに合わせ最適化した。また、NSリング、蓄積リングシングルバンチ用1nsグリッドパルサーと蓄積リングFull-fill用40nsパルサーをリモートで切り替えるようにし、両リングの入射を短時間に切り替えられるようにした。
これら改造の結果、1GeVでの電子ビームのエミッタンスは0.05πmm・mradとなり、以前のエミッタンスの約50%になった。ビームモードの切り替え時間もNS入射モードからSR入射モードへは約10分程度、SR入射モードからNS入射モードへは偏向電磁石の消磁、初期化などの作業が入るものの約30分で行えるようになった。また、100mA以下の電流も安定して出すことが出来るようになったため、下流の電流調整用スリットでビームを削る割合も減少し、残留放射能による被曝の可能性を減少させることが出来た。
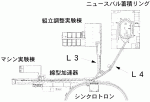
図1 L3、4平面図

図2 L3、L4分岐部
左のビームラインがL3BT。図3に示されるビームダンプへ至る。右のビームラインがL4BT。図4に示されるL4BTトンネルを経由してNSリングへ至る。

図3 L3BTダンプ部
電子は手前の偏向電磁石で地下にあるビームダンプへ送られる。

図4 L4BT
中央に見える偏向電磁石でNSリング方向へ曲げられる。トンネル内はL3BTに比べかなり狭い。
3.ビームトランスポートラインの概要
新規のビームトランスポートラインは2本で、L3、L4と呼ばれる(図1、2、3、4参照)。両方のビームトランスポートラインを合わせて、セクター型偏向電磁石5台、ボーア径の異なる3種類のQ電磁石が27台、ステアリング電磁石14セットよりなる。また、100R/sのイオンスパッタポンプ10台でビームトランスポートラインの真空を保持している。ビームモニターとしては蛍光板モニター14台、短パルス型コア式電流モニター3台、ストリップライン型ビーム位置モニター2台より形成されている。
L3は線型加速器のL2ビームダンプの直前で左に3台の偏向電磁石で30度ずつ計90度曲げられ、組立調整実験棟方向に導かれるラインである。このビームトランスポートラインは、電子ビームのモニター及びビーム物理研究用のビームトランスポートラインとなる。このラインはアクロマート系またはアイソクロナス系を組むことができ(図5参照)、短バンチの電子ビームの輸送が念頭に置かれており、将来のSASEなどの計画に耐えるものになっている。電子ビームが導かれる組立調整実験棟は以前の利用者情報Vol.2 No.2に北見氏より紹介されてるが、壁面の一部が、3mの遮蔽壁になっている。今回の計画では組立調整実験棟内部まで電子ビームを輸送することは行っていない。実験棟手前のトンネルの床に穴が掘られており、その中にビームダンプが収納されている。電子ビームは偏向電磁石によって下方向に30度曲げられ、ビームダンプに入射される。このビームダンプは電気的に絶縁されており、ファラデーカップとして電流測定を行う。L3トンネルへの出入りは組立調整実験棟の組立実験室より行う。このビームトランスポートラインのあるトンネル内へは、シンクロトロンへの入射中であってもトンネル内にあるゲートまでは入室できるため、各種実験のセットアップがやりやすい状況になっている。

図5 L3系ラティス計算
L3ビームトランスポートラインのコミッショニングは平成10年9月18日より始められ、約1時間の調整後、電子ビームはビームダンプまで輸送されたことが確認された。磁石のアライメントを0.2mm以下の精度で行ったため、ステアリング電磁石もほとんど励磁することがなく、途中のビームロスも少なく、放射線安全上、問題になるほどではなかった。
L4はニュースバルへの電子ビーム輸送ラインで2台の偏向電磁石により30度ずつ計60度曲げられる。L3の最初の電磁石は共通で、2台目の電磁石を励磁するかしないかでL3とL4を振り分ける。このビーム輸送系は偏向電磁石間に8台のQ電磁石が配置され、アクロマート系が形成されている(図6参照)。
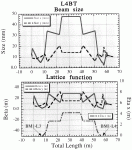
図6 L4系ラティス計算
線型加速器ではP点と呼ばれるポイントまでビーム輸送し、あとはNSリング側での制御となる。NSリングとの取り合いをはっきりさせるため、約8m離れた2台の蛍光板モニターの中心を通すことにより、ビームトランスポートラインの軸を押さえている。
L4ビームトランスポートラインのコミッショニングは9月21日より始められた。こちらは放射線安全上、一週間あたりの輸送電荷量に制限があるため、1ショットごとにビームを打ち、蛍光板モニターで確認して次へ進むという方法を取るためにかなりの時間を要した。とはいえ、取りあえず輸送し、NSリングに制御権を渡すP点までは数時間で行き着くことが出来た。その段階では完全にアクロマート系が組みきれておらず、30cm程度のディスパージョンが残っていたが、後日、再調整を行い、それもほとんどなくすことが出来た。
これらのビームトランスポートラインの制御は、線型加速器の延長とし、WS-VMEの構成による、線型加速器と同等の制御を行っている。制御の画面もGUIを一部拡張し、線型加速器と一体として制御できるようになっている。
4.ニュースバルへの入射
平成10年12月末現在、NSリングはコミッショニング中であり、フィジカルアパーチャーのサーベイ、チューンの測定、CODの補正等の段階を経て、約1.3mAの電流蓄積がなされている。ビームの寿命はNSリング内の真空度が悪いため、まだ数分程度であるが、冬期停止期間中に温水ベーキングを行いさらに延びる予定である。今後は入射効率の向上、さらに詳細なCOD補正等を行い、寿命を延ばした段階で使用時検査を受け、ユーザーに供給される予定である。
5.今後の計画
線型加速器は入射器としての使命が第一である。その負担は、従来のシンクロトロン蓄積リングに加え、NSリングも加わり倍増した。そのために、線型加速器のさらなる安定化や故障時に速やかに対応出来るような電子銃、バンチャー部の2重化を行っていく必要があると考えている。
しかしながら、入射及び入射の時間の準備などで必要な時間は蓄積リングで1日1、2回1、2時間くらいであり、NSリングの入射もその程度になることが予想される。それ以外の時間は空き時間となるので、L3ビームトランスポートラインを利用し、超短バンチビームの計測技術の開発、レーザー逆コンプトン光の発生、パラメトリックスX線など様々な利用が考えられる。これらの研究、利用に外部の研究者も取り込んでいき、それらの要望に応えられるような短バンチ化、低エミッタンス化等の線型加速器の高度化を推し進めていきたい。
鈴木 伸介 SUZUKI Shinsuke
昭和35年11月16日生
(財)高輝度光科学研究センター 加速器部門
〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町三原323-3
TEL:07915-8-0867 FAX:07915-8-0850
e-mail:shin@haru01.spring8.or.jp
略歴:平成3年東北大学理学研究科原子核理学専攻博士課程後期修了、同年日本原子力研究所入所、平成8年(財)高輝度光科学研究センターに出向。
趣味:酒、睡眠、アウトドア








