Volume 03, No.5 Pages 24 - 26
5. 研究会等報告/WORKSHOP AND COMMITTEE REPORT
第6回 European Particle Accelerator Conference (EPAC’98) 参加およびBESSYII, SINCROTRONE TRIESTE, ESRF を訪問して
On Participating in EPAC’98 and Visiting BESSYII, SINCROTRONE TRIESTE and ESRF
表記の会議が、6月22日より5日間にわたり、スウェーデンのストックホルムCity Conference Centreで開催された。参加人数は約650名で発表論文件数は約900編である。EPACはもともとアメリカで2年に一度開催されていたParticle Accelerator Conference(PAC)に対抗(?)してヨーロッパでも始めたもので、第1回が1988年にローマで、その後ニース、ベルリン、ロンドン、バルセロナと隔年で開催されてきたものである。筆者達(妻木、原)は第1回のローマの会議に参加したが、その時に比べ今回の参加人数が少なく感じたため調べてみたら50人ほどではあるが減っていた。主催者側も第1回のAsian Particle Accelerator Conference(APAC)が今年の3月に開催されたことや、アジアの不況でアジアからの参加者が減ったのではないかと心配していたそうである。

写真1 Banquet の開かれた市庁舎の庭で、ガムラスタンを背景に、左から島田、妻木、原、高雄。この市庁舎の広間でノーベル賞授賞式の晩餐会が開かれる。
発表は、招待講演、一般講演、ポスターセッションにわかれ、講演は初日と最終日は大ホールで、その他は大ホールを二分して行われた。ポスターセッションはいくつかの部屋に別れて行われた。論文は、(1)加速器と蓄積リング、(2)サブシステム、テクノロジーおよびコンポーネント、(3)ビーム力学と電磁場、(4)加速器の応用、の4つに大分類され、各々はさらに6項目から19の項目に分類されていた。招待講演は次のような項目にわかれていた。(1)高エネルギーハドロンおよび重イオン加速器とコライダー、(2)放射光と自由電子レーザー(3)リニアーコライダー、(4)ビーム力学とオプティックス、(5)インスツルメンテイションとフィードバックシステム、(6)加速器の応用、(7)加速器技術、(8)レプトンコライダー、(9)中および低エネルギー加速器と粒子源、(10)大強度プロトンマシンおよび粒子源、(11)アドバンストコンセプト、(12)産業界のためのセミナー:将来の加速器プロジェクトの工業的な期待。これからもわかるようにこの会議は加速器に関係したほとんどすべての項目を網羅しているが、放射光関係以外は関心のない方が大部分であると思われるのでここでは放射光関係の加速器の話題を簡単に紹介させて頂くのにとどめる。
ESRFからSOLEILに移ったLaclareが、建設の終わった第3世代の放射光リングの性能と次につくる場合の参考となる点について招待講演を行った。第3世代リングの設計時の課題は、誤差に対するsensitivityの高さや、ダイナミックアパーチャーの小さいことなどであったが、これらの問題はクリアされ、いずれのリングも最初の目標性能を満足している。今後はエミッタンスを回折限界により近づける努力が必要になる。エミッタンスが小さくなるとビームの安定度、特に垂直方向の軌道の変動を1μm以内にする必要があること、冷却水の温度変化を小さくすること、ビーム位置モニターの安定性を増す必要があることなどを述べた。さらにエミッタンスが小さくなるにつれビーム寿命が短くなるため、エネルギーアクセプタンスを増やして長寿命化をはかることや、パーマネント入射を考える必要があることなどについても言及した。特にこれらは目新しいことではないが、当面これらを地道にやるしかないだろう。
Laclareの講演通り、第3世代のリングは予想以上にうまくいっている感がある。SPring-8でもアラインメントのデータを基に、補正をしない場合の閉軌道のずれやカップリングをおおよそ計算でき、その結果これらの値が小さな値になることはわかっていた。しかし実際に観測された値は計算と同じか、計算より小さな値になっている(未確定要素のため、計算より大きくなるのが普通だと思うのだが)。不思議に感じるのは筆者達だけであろうか。
その他UCLAのPellegriniの「Is the High Gain FEL the 4th Generation Light-Source?」と魅惑的な題名の発表があり、SASE FELで2002年以降には数nmの波長のX線FELが得られるだろうとの話があった。またTRIESTEのWalkerが放射光とFELのプロジェクトのレビューを行なった。その中で日本のほとんどのリングが引用されており、この分野における日本の占める割合の大きさを改めて実感した。
EPAC終了後、BESSYII, SINCROTRONE TRIESTE, ESRFを訪問した。BESSYIIはBESSYIの後続機として同じベルリンではあるが、旧東独側に建設されたエネルギー1.9GeV、エミッタンス6nmの第3世代のリングである。BESSYIIではKRAMER氏に案内して頂いた。氏によると今年の4月20日にコミッショニングが始まり、翌日にはビームが一周し、翌翌日には蓄積できたとのことである。我々が訪問した時はリニアーオプティックスのマシンスタディの実施日であったが、ちょうどビームが停止していたためリング内を見ることができた。すでに挿入光源が2台設置されており、来年3〜4本の挿入光源のビームラインと6〜8本の偏向電磁石のビームラインがユーザーに解放されるとのことである。リングは少し雑然とした印象を持ったが、あれで大丈夫なのであろうか。
BESSYII訪問後イタリアTRIESTEにあるSINCROTRONE TRIESTE のELETTRAを訪問した。我々が訪問した日はSWISS LIGHT SOURCE に移ったWRULICH氏の後任のTAZZARI氏がローマからきており、案内をして頂いたBOCCHETTA氏も忙しそうであった。 TAZZARI氏は常勤ではなく週のうち数日ローマから出張してくるらしい。さてBOCCHETTA氏によると蓄積リングは一日一回入射で、蓄積電流はマルチバンチで300mA、シングルバンチで60mAである。カップリングも0.6%と小さくビームサイズが小さいため、寿命が短くなってしまうが、幸か不幸か縦方向の不安定性のため、エネルギー幅が広がり寿命が伸びている。そのためあえて不安定性を抑えこんではいない。一番の問題はビーム電流の減衰に伴い真空チェンバーの熱負荷が変わり、位置モニターが水平方向に60μm近く動いてしまうことである。そのためシンクロトロンを作って2GeVのfull energy入射でtop up運転を検討しているとのことだった。
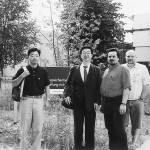
写真2 BESSY-IIの看板を前に左から高雄、妻木、原、D.KRAMER、D.RICHTER。BESSY-IIはベルリンの郊外(旧東ベルリン)のALDERSHOF に新しく建設され、スタッフのほとんどは引っ越したばかりであった。
TRIESTEでは佐々木茂美氏にお世話になり、佐々木氏の住んでいる村のTRATTORIAで本場のピザとアイスクリームをご馳走になった。ちなみにTRATTORIAは佐々木氏の愛嬢のまほちゃんによると、BARとRISTORANTEの中間に位置するとのことである。ついでに言えばまほちゃんは小学校六年生であるが、我が一行の某氏は何を勘違いしたか、イタリアでは小学生でも香水をつけているんではないかと、おみやげにシャネルの5番を買っていった。しかし結局まほちゃんのピアノの先生へのプレゼントになりそうな気配であった。
TRIESTEのあとESRFを訪問した。ESRFでは昔理研で一緒に仕事をした長岡さんが駅まで迎えにきてくれた。駅の近くのベトナム料理屋(?)で昼食を食べながら長岡さんが言うには、SPring-8の現状についてプレゼンテーションをやるようにお願いしたが、今日はサッカーのワールドカップのイタリアとの試合があり、出席者があまりいないかもしれない、とのことだった。筆者もそのほうが気楽で良いと思ったのであるが、昼食後セミナー室に行くと意に反して人が一杯で、急遽場所を一番大きな部屋に変更することになった。大体30名強の人が集まりSPring-8への関心の高さが伺えた。プレゼンテーションは、リングの概要とコミッショニング(試験調整運転)について簡単にふれたあと、ビーム不安定性、ビームの位置の安定度、カップリング(垂直方向のエミッタンス)などの現状について説明した。コミッショニングまでは質問もほとんどなかったが、ビームの不安定性、位置の安定度と話をするにつれ真剣な質問が増え、カップリングの話の時などはしつこい位であった。要はカップリングを例にとれば、ESRFが何年かかけて到達した値より、SPring-8で何もしないナチュラルな値のほうが小さかったので彼等には信じられなかったのかもしれない。カップリングは六極電磁石のアラインメントエラーによる寄与が一番大きいのであるが、SPring-8ではこの寄与がキャンセルするようなアラインメントの方法をとっており、もう一つの要因である四極電磁石の傾きも通常より1オーダー小さくしてある、と答えたがどこまで納得してもらえたか疑わしい。プレゼンテーション終了後、長岡さんが話してくれたところによると、前でよく質問していたのが所長のPETROF氏でおもだった人は全員出席しており、彼等にとってSPring-8のクオリティが自分達と同じかより優れていたためかなりショックだったのではないかとのことだった。なれない英語で一時間以上も話したため疲れはててしまい、休みたかったが引き続き長岡さんと軌道解析のFarvacqueにESRFの現状について説明してもらったり、ディスカッションしたりした。その結果Farvacqueにはある程度信じてもらえたようで、俺達が何年間かfightして到達したレベルあるいはそれ以上のところにおまえ達はいると言ってもらえた。
SPring-8は第3世代のリングであるが現状でも3.3世代位のところに到達していると言ってよいのではないだろうか。SPring-8をさらに第4世代まで近づけるとともに、本当の第4世代、さらには第5世代を目指していくのが、この幸運な立場にいる我々の権利でもありまた義務でもあるだろう。いつの日かこの西播磨の地が放射光の世界のメッカとなり、放射光関係で重要な結果がSPring-8から次々にでる、そんなふうになったらなんてすばらしいんだろう。そんなことを考えながら二週間の旅を終え、ヨーロッパをあとにした。
妻木 孝治 TSUMAKI Koji
(財)高輝度光科学研究センター 放射光研究所 加速器部門
〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町三原323-3
TEL:07915-8-0886 FAX:07915-8-0850
e-mail:tsumaki@sp8sun.spring8.or.jp
高雄 勝 TAKAO Masaru
(財)高輝度光科学研究センター 放射光研究所 加速器部門
〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町三原323-3
TEL:07915-8-0860 FAX:07915-8-0850
e-mail:takao@sp8sun.spring8.or.jp
島田 太平 SHIMADA Taihei
(財)高輝度光科学研究センター 放射光研究所 加速器部門
〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町三原323-3
TEL:07915-8-0886 FAX:07915-8-0850
e-mail:shimada@sp8sun.spring8.or.jp
原 雅弘 HARA Masahiro
(財)高輝度光科学研究センター 放射光研究所 加速器部門
〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町三原323-3
TEL:07915-8-0863 FAX:07915-8-0850
e-mail:hara@sp8sun.spring8.or.jp








