Volume 08, No.1 Pages 3 - 19
1. SPring-8の現状/PRESENT STATUS OF SPring-8
第11回(2003A)利用研究課題の採択について
The Proposals Accepted for Beamtimes in the 11th Public Use Term 2003A
財団法人高輝度光科学研究センターでは、利用研究課題選定委員会による利用研究課題選定の結果を受け、以下のように第11回共同利用期間における利用研究課題を採択した。
1.募集及び選定日程
(募集案内・募集締切)
9月17日 利用研究課題の公募について
SPring-8ホームページに掲示
(一般課題)
10月26日 一般課題募集締切り(郵送の場合、当日消印有効)(10月28日10時必着)
(特定利用課題)
10月10日 特定利用課題募集締切り
10月15~21日 特定利用分科会による書類審査
10月29日 特定利用分科会による面接審査
(一般課題及び特定利用について課題選定及び通知)
11月21、22日 分科会による課題審査
12月10日 利用研究課題選定委員会による課題選定
12月16日 機構として採択し、応募者に結果を通知
2.選定結果
今回の公募では733件の課題応募があり前回よりもやや少なかったが、採択件数は563件とこれまでの最高となった。ここ数年、1年の前半の共同利用期間(A期)では応募が少なく、反対に後半(B期)では大幅に増加する傾向が続いていた。今回も同様の傾向となっている。連続する2回の公募状況を足し合わせ1年単位でまとめたのが次の表である。応募課題数及び採択課題数は、年とともに増加している。
応募課題数 採択課題数
第10回+第11回(平成14年9月~15年7月) 1,484 1,037
第8回+第9回(平成13年9月~14年7月) 1,262 977
第6回+第7回(平成12年10月~13年6月) 1,084 789
第4回+第5回(平成11年9月~12年6月) 855 572
今回の公募では成果専有利用の応募が2件あり、また特定利用への応募が4件あった。第1回から今回の公募までの、分野別及び所属機関別の応募数及び採択数を表1に示す。また、関連するデータをグラフ化して図1、図2に示す。
今回の採択結果は、件数では応募733件に対し採択563件(採択率77%)であった。また、採択された課題(タンパク3000課題(シフト枠は318シフト)を除く)のシフト数では要求5,655シフトに対し配分4,836シフト(平均のシフト充足率86%)であった。また、採択された課題の平均シフト数は9.5と前回の8.7より大きくなっている。利用研究課題選定委員会では、従来より採択された課題の要求シフト数と配分シフト数の比(シフト充足率)を出来るだけ大きくする方針のもとに選定審査が行われている。今回、平均のシフト充足率は86%であり、前回の78%よりさらに向上した。
研究分野別の採択課題数は、生命科学、散乱・回折、分光、XAFS、実験技術、産業利用の順であり、タンパク3000課題を含む生命科学が散乱・回折を上回った。また、採択課題の実験責任者の所属機関別では、国立大学が全体の半数近くを占めておりこれまでと大きくは変わっていないがやや割合を減らした。今回は特に、民間と海外がこれまでより割合を大きく伸ばした。
今回の共同利用で対象としたビームライン毎の応募・採択課題数、課題採択率、採択された課題の要求シフト数・配分シフト数、シフト充足率、平均シフト数を表2に示す。採択課題数の多かったビームラインは、BL41XU(構造生物学Ⅰ)の49件(1課題あたり2.9シフト)、BL40B2(構造生物学Ⅱ)の36件(1課題あたり5.2シフト)、BL02B2(粉末結晶構造解析)の36件(1課題あたり5.3シフト)、及びBL01B1(XAFS)の33件(1課題あたり6.9シフト)であった。これらのビームラインでは当然ながら1課題あたりの配分シフト数は平均シフト数9.5より少ない。ビームラインごとの採択率が低かったのはBL19B2(産業利用)の44%であり、以下BL02B1(結晶構造解析)50%、BL25SU(軟X線固体分光)58%と続く。平均のシフト充足率は、前述のように今回の審査では前回より向上したが、その中で応募課題数が多くシフト充足率の低かったビームラインは、BL02B2(粉末結晶構造解析)61%、BL40B2(構造生物学Ⅱ)62%、BL41XU(構造生物学Ⅰ)64%等である。表3に、所属機関別に各研究分野毎に応募・採択数をまとめて示す。これにより、民間からの各分野への応募・採択状況と、産業利用分野への各所属機関からの応募・採択状況がわかり、今回の民間又は産業利用の応募は73件で採択が47件(採択率64%)であった。前回の民間又は産業利用の応募は81件で採択が38件(採択率47%)であったので、今回は応募件数が減少したが採択件数は増加している。
特定利用(通常課題の実施有効期限が6ヶ月であるのに対し、3年以内の長期にわたって計画的にSPring-8を利用することによって顕著な成果を期待できる利用)では、今回の公募で4件の応募があり、そのうちから1件が採択された。審査は外部の専門家を含む特定利用分科会での書類審査、及び面接審査の2段階で行われた。採択された課題については概要を後述する。
成果専有利用として民間から2件の応募があった。この課題について公共性・倫理性の審査と技術的実施可能性及び実験の安全性の審査が行われ全件採択された。
表1 利用研究課題公募内訳
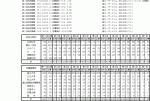
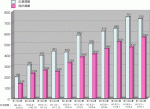
図1 各公募時における応募課題数と採択課題数
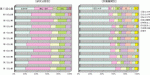
図2 採択課題の研究分野別所属機関別分類
表2 ビームラインごとの採択状況
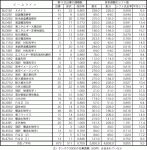
表3 2003A応募課題数と採択課題数:研究分野と機関分類
3.利用期間
年間の前期と後期の共同利用の利用時間に長短のアンバランスが通常以上に大きくなることを緩和するためこれまでと同様に、今期も第1サイクル途中からとなっている。このため、今回募集した第11回(2003A)共同利用の利用期間は2003年第1サイクル途中から2003年第5サイクルまで(平成15年2月から平成15年7月まで)となり、この間の放射光利用時間は285シフト(1シフトは8時間)となっている。このうち共同利用に供されるビームタイムは共用ビームライン1本あたり228シフトとなる。
4.利用対象ビームライン及びシフト数
今回の募集で対象としたビームラインは総計33本でその内訳は、今回から正式に募集したBL37XU(分光分析)を含む共用ビームライン25本(R&Dビームライン3本を含む)とその他のビームライン8本(原研ビームライン3本、理研ビームライン4本、及び物質・材料研究機構ビームライン1本)であった。
今回の採択では、これまでと同様に、生命科学分科における蛋白質結晶解析に使用する分科会留保シフトをBL41XU(構造生物学Ⅰ)で設けたこと、産業利用に留保シフトを設けたこと、及び昨年度からナノテクノロジー総合支援プロジェクト及びタンパク3000プロジェクトに対応する応募課題を含めたことなどから共同利用として採択された全課題の配分シフト数の合計は表2に示すように4,836シフトとなった。但し、タンパク3000プロジェクト関係の課題はシフト枠が318シフトと確定しているが、個別の課題への割振調整は今後行われるので前記の配分シフト数の合計には含めていない。表1の総ユーザータイムは両者を加えて、約5,200シフトとしている。
5.生命科学分野及び産業利用分野におけるビームタイムの留保
生命科学分野におけるSPring-8の利用では、特に実験試料の特殊性から、短い時間でもいいから試料の出来具合をチェック出来るような利用をしたい、試料が出来たときに緊急に利用したいと言った要望が強い。このような要望に応えて、今回もBL41XU(構造生物学Ⅰ)で23シフトのビームタイムを留保した。
また、前回から産業利用分野への応募を一般課題募集時から行っており、今回は17課題に114シフトを配分したが、前回までと同様の留保枠も114シフトを確保した。
6.ナノテクノロジー総合支援プロジェクト及びタンパク3000プロジェクト
(1)ナノテクノロジー総合支援プロジェクト
昨年より実施されている「ナノテクノロジー総合支援プロジェクト」は、ナノテクノロジー分野の振興に資するため、個別の研究機関や研究開発プロジェクトでは整備の難しい大型・特殊な施設・設備とその利用に関する高度な技術を活用できる環境を整える事を目的としている。
大型放射光施設SPring-8では、「共用ビームラインを活用した放射光利用解析支援」として、ナノテクノロジー分野に特化した支援実施に適したビームラインを活用し、利用研究支援を行う。今回は応募課題数92件に対して選定課題数が60件で選定率65%シフト充足率87%となった。
(2)タンパク3000プロジェクト
ポストゲノム戦略の中核として我が国発のゲノム創薬の早期開発の実現等を目指し、我が国の研究機関の能力を結集して特許化までを視野に入れた研究開発を推進するために、平成14年度から文部科学省の「タンパク3000プロジェクト」が始まった。このプロジェクトは日本全体で5年間に、全基本構造の3分の1にあたる約3000種類以上のタンパク質の構造および機能を解析することを目標にしている。この内、SPring-8ではタンパク質の解析に必要な放射光をプロジェクトに参加する研究機関に供与する。
今回平成14年度内の調整として、2月、3月にタンパク3000関係課題を多く入れ、4月以降は平成15年度の年間計画に沿ったシフト数を割当てた。
7.産業界の利用
表3に示すように今回の公募で、民間からは各研究分野に合わせて55件の応募があり、40件が採択された。前回が応募56件で採択29件であったことと比較して、今回は民間からの課題の応募数が前回とほぼ同じで採択数は11件も増加したので採択率は73%となり全体平均と同程度となった。しかしながら、産業利用分野の課題は対象ビームラインが1本(BL19B2)で留保ビームタイムも取るので、各研究機関から合わせて39件の応募に対して17件の採択で、採択率が44%と前回同様低くなっている。両者を合わせて、今回の民間からもしくは産業利用分野いずれかへの応募総数は73件で、採択総数は47件であった。今回の採択総数47件は前回の38件より伸びている。
8.課題選定審査における留意点
(1)前回からBL02B1(結晶構造解析)における1年課題の募集をしている。これは、回折・散乱分科1では半年では終了しない課題が大半を占めており、シフト数の要求の少ない課題でも2回実験を行うことに重要な意味があるためで、2年間試行することとした。今回は前回採択の1年課題の後半期が実施されるので、2003A期のみの課題が公募され16件の応募に対して8件(84シフト)が採択された。
(2)XAFSにおける試しの必要な課題のための分科留保は、今回1件採択した。
(3)BL37XUとBL40XUにおいては、採択課題の配分シフト合計が配分可能シフト数より、それぞれ39シフトと20シフト少なかった。これは、これらのビームラインを希望する応募課題数が少なかったことによるので、今後、再募集を考える。
(4)課題選定では、1課題に十分な実験時間を確保するために、選定された課題の要求シフトに対する配分シフトの比率(シフト充足率)を確保することにつとめた。また、前回同様、平和目的の確保、挑戦的な課題の確保を念頭に置いた審査を行った。
9.特定利用課題の選定
2000B共同利用から開始したSPring-8特定利用については、今回は1件の課題が選定された。今回採択された課題は、平成15年2月から3年以内の期限で実施していただくものである。今回選定された研究課題の概要を以下に示す。
課題番号:2003A0013-LD2-np
課 題 名:100万気圧以上における高温その場観察実験の開発と地球惑星内部物質の相転移の研究
実験責任者:巽 好幸(海洋科学技術センター)
利用ビームライン:BL10XU
3年間の要求シフト数:252シフト
2003Aの要求シフト数:42シフト(配分30シフト)
研究概要:
地球を構成するマントルとその金属核の境界での圧力・温度は、135万気圧3000K以上に達しているとされる。高輝度X線を用いたその場観察実験から導き出される超高温高圧下における物質の安定な結晶構造、圧縮率、熱膨張率などの結果から、地球や惑星深部の層構造をはじめて解明できる。しかしながら、100万気圧を超える圧力と2000K以上の高温高圧の状態におけるX線その場観察の報告例はきわめて限られており、ほぼ未知の世界である。
本研究では、100万気圧以上の超高圧下における高温実験の技術開発を積極的に行う。具体的には、300万気圧・4000Kにおけるその場観察実験を目指し、Nd:YLFレーザーの導入とX線集光光学系の整備を行う。
それにより、マントルの底にあたる135万気圧・2500Kまでの温度圧力範囲でパイロライトのその場観察実験の実施、マントルと化学的に大きく異なる玄武岩海洋性地殻の下部マントルにおける密度の決定、地球の内核(固体鉄)・外核(融解鉄)の温度を制約する重要なデータとして300万気圧までの鉄の融解曲線の決定、地球の核の温度圧力条件に相当する300万気圧・4000K間での条件でX線回折その場観察実験を行い、鉄及び軽元素の系における安定な相とその結晶構造・相転移の解明を行う。
また、技術開発の成果を他分野へ積極的に公表すると同時に実験技術の普及を行うことで、超高温・高圧条件を利用した材料科学・新物質開発の分野の発展にも貢献したい。
課題選定委員会での審査結果:
本提案は、地球科学上のメリット及び高温高圧技術開発の点で高く評価でき、実験遂行においてSPring-8が高温高圧科学のセンターになり得ることが期待される。ただし、本研究分野において先行しているとされるAPSの研究レベルを追い越すための具体的戦略が必要であろう。
10.採択課題
表4に今回採択された利用研究課題の一覧を示す。配分シフト数欄の「nano」の付いた課題はナノテクノロジー総合支援プロジェクトの課題であり、「p3k」の付いた課題はタンパク3000プロジェクトの課題である。
表4 2003A期に採択された利用研究課題一覧
nano:ナノテクノロジー総合支援プロジェクト
p3k :タンパク3000プロジェクト
詳しくは、PDFファイルをご参照下さい。








